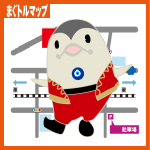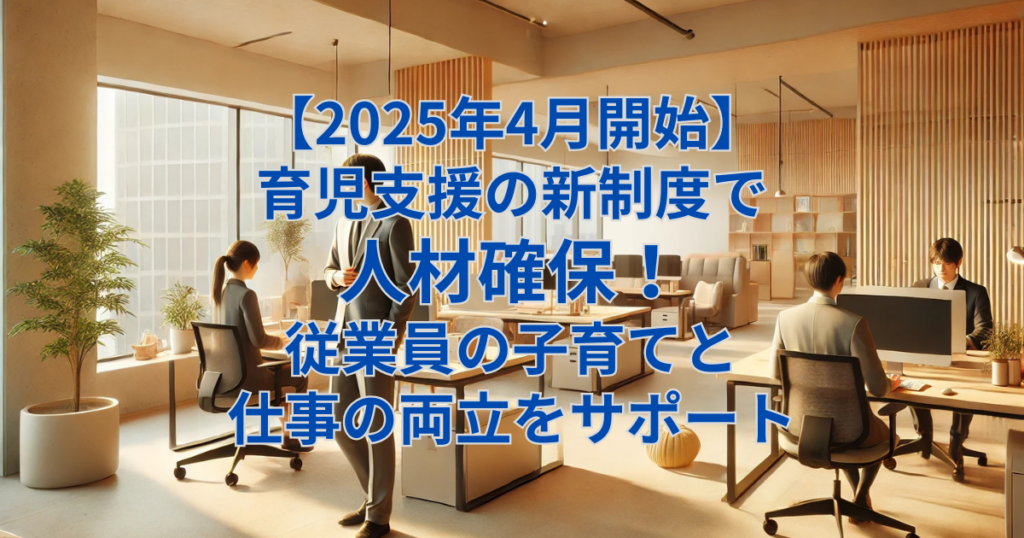
「従業員の育児休業、どう対応すればいいのか…」「時短勤務の要望があるけれど、会社の負担が心配」――こんな悩みを抱えている事業主の方も多いのではないでしょうか。
人手不足が深刻化する中、優秀な人材の確保・定着には、育児と仕事の両立支援が不可欠となっています。しかし、経営資源の限られた事業者にとって、その対応は大きな課題となっているのが現状です。
そんな中、2025年4月から、事業主の負担を軽減しながら従業員の子育て支援を実現できる、新しい給付金制度がスタートします。これは、人材確保に悩む事業主の皆様にとって、とても重要な制度になると考えています。
この記事では、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」について、実務的な観点から分かりやすく解説します。記事を読むことで、1)新制度の具体的な内容、2)御社での活用方法、3)申請手続きのポイントが理解できます。
経営者の皆様の不安を少しでも解消し、従業員が安心して働ける職場づくりにお役立ていただければと思います。ぜひ最後までお読みください。
目次
新制度導入で変わる!従業員の働きやすい職場づくり

2025年4月から始まる育児支援の新制度には、主に「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」の2つがあります。これまで育児支援の制度づくりに踏み切れなかった事業主の皆様も、この機会に前向きに検討してみませんか。
この新制度の活用で期待できる効果をご紹介します。
【事業主・会社側のメリット】
- 優秀な人材の確保・定着につながります
- 「子育てに理解のある会社」として評判向上が期待できます
制度を利用する従業員は、育児休業中の賃金保障(最大80%)や時短勤務時の収入補填により、安心して仕事と育児を両立できる環境が整います。
実は、こうした制度の導入は、職場全体の働き方を見直すきっかけにもなります。従業員一人一人が、より効率的に、そしてやりがいを持って働ける職場づくりにつながっていくのです。
まずは御社の状況に合わせて、できるところから始めてみてはいかがでしょうか。
お父さんもお母さんも安心して取得できる!出生後の育児休業支援

「育休を取りたいけど、給料が減るのが心配…」 「共働きだから、夫婦のどちらかは働かないと…」
従業員からこんな声を聞いたことはありませんか?
2025年4月からスタートする「出生後休業支援給付金」は、そんな不安を解消する制度です。両親がともに育児休業を取得した場合、休業中の賃金の最大80%が保障されます。つまり、お父さんもお母さんも、経済的な心配を減らしながら、赤ちゃんとの大切な時間を過ごすことができるのです。
14日以上の育児休業を取得すれば対象となりますので、従業員の方々にもぜひお知らせいただければと思います。
子育て中の従業員を支援!時短勤務をサポートする新制度

保育園の送り迎えのため、フルタイム勤務が難しい従業員はいませんか?子育て中の従業員の時短勤務については、会社としても前向きに検討したいところですが、従業員の収入減少が気になるところです。
そこで注目なのが「育児時短就業給付金」です。2歳未満のお子さんがいる従業員が時短勤務を選択した場合、減少した賃金の一部(賃金の10%)が給付金として支給されます。
たとえば、午前10時から午後4時までの時短勤務や、週3日勤務といった柔軟な働き方も選択しやすくなります。従業員にとっては収入面の不安が軽減され、会社としては貴重な戦力の確保につながる、いわば「WIN-WIN」の関係を築くことができます。
まだ子育てと仕事の両立に悩む従業員の方がいらっしゃれば、この制度を一度ご検討されてはいかがでしょうか。
まとめ:新制度で実現する、選ばれる会社づくりのヒント

2025年4月からスタートする育児支援の新制度について、そのポイントを整理してみましょう。
【この記事のエッセンス】
- 出生後休業支援給付金
- 両親での育児参加を経済的に支援
- 休業中の賃金最大80%を保障
- 14日以上の取得で対象に
- 育児時短就業給付金
- 2歳未満の子を持つ従業員が対象
- 時短勤務による減収を補填
- 柔軟な働き方の選択肢が広がる
人手不足が深刻な今、この制度をうまく活用することで、「子育て世代に選ばれる会社」として一歩前に進むチャンスかもしれません。まずは御社の従業員構成や、今後の採用計画なども踏まえて、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
───────────────
【参考資料】
- 厚生労働省リーフレット:育児時短就業給付金」を創設します
- 厚生労働省リーフレット:出生後休業支援給付金を創設します
- 制度の詳細は厚生労働省Webサイトをご確認ください 育児休業等給付について